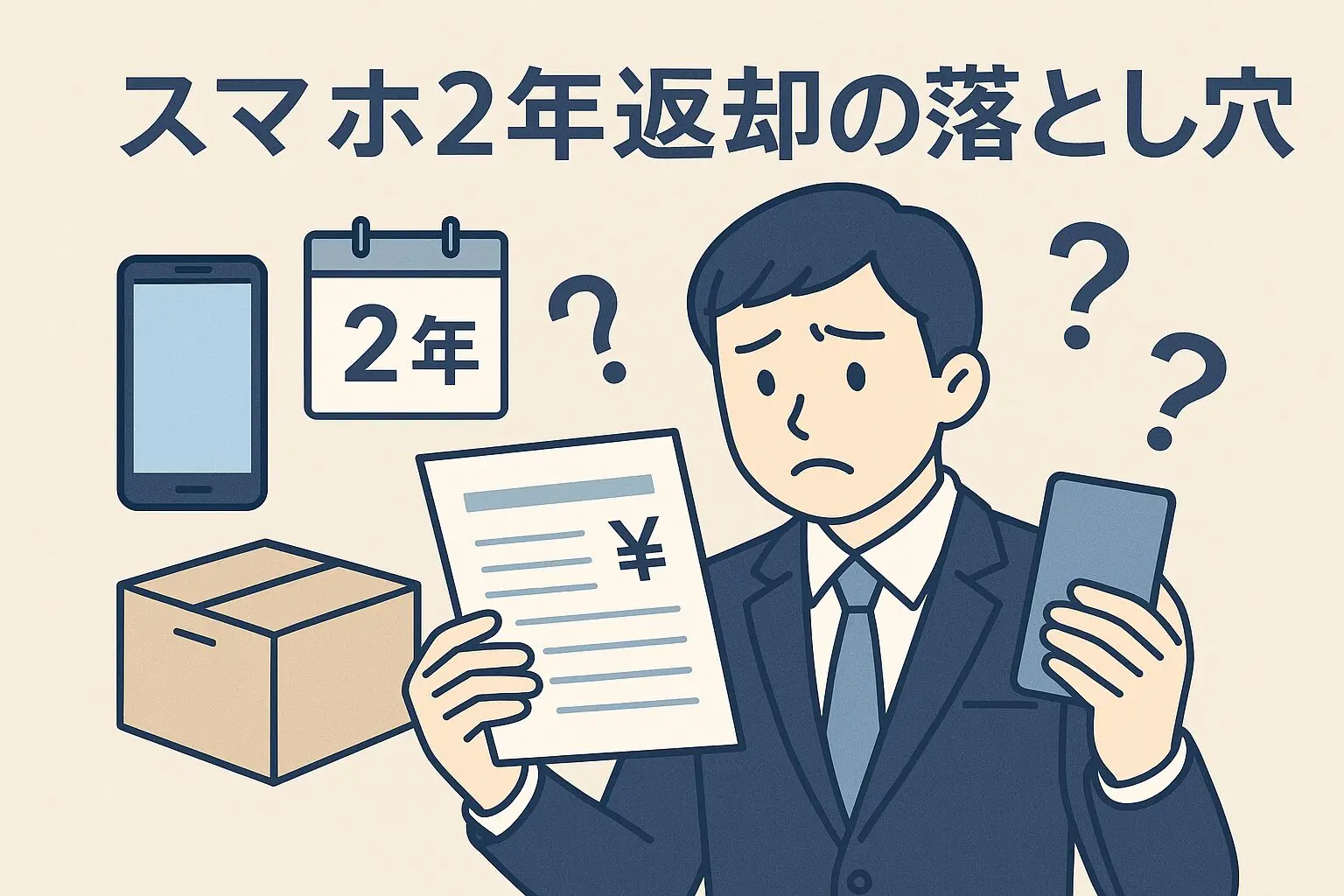イントロダクション
近年、ドコモ・au・ソフトバンクといった大手キャリアで急速に広まっている「スマホ2年返却プラン」。新しいスマホを実質的に安く手に入れられるとして人気を集めていますが、その裏には見逃せないデメリットが潜んでいます。
筆者自身もかつて、自動車の残価設定ローン(いわゆる「残クレ」)を利用した経験があります。そのときは、わずかな小傷や内装の汚れでも「査定不良」とされ、数万円単位の費用を請求されました。この経験から、スマホの2年返却プランにも同じようなリスクを感じています。
この記事では、「スマホ2年返却プランは本当にお得なのか?」「どんな落とし穴があるのか?」を、筆者の実体験と公式情報をもとに詳しく解説します。これからスマホを買い替える方に向けて、後悔しない選び方をお伝えします。
この記事のポイント
- スマホ2年返却プランは実質“レンタル”であり、所有権は利用者にない
- 「ゼロ円返却」には厳しい査定条件がある
- 途中解約や返却遅延で想定外の高額負担になる
- 返却しない場合、残価分の支払いが発生して結局割高になる
スマホ2年返却デメリットとは?一見お得に見える仕組みの裏側

まず、このプランの仕組みを整理しましょう。スマホ2年返却プランとは、購入したスマートフォンを「2年間使用した後に返却すること」を条件に、残価(2年後の想定下取り価格)を差し引いた価格で契約できる仕組みです。返却すれば残りの分割支払いが免除されるため、表面的に“半額で最新機種が使える”ように見えます。
実は「割引」ではなく「条件付き免除」
注意すべきは、これはあくまで「残債免除の特典」であり、“割引”ではないという点です。返却せずに使い続ける場合は、残価分も含めて全額支払うことになります。したがって、実際には「レンタル契約に近い」形態です。
例えば、15万円のスマホを2年返却プランで契約した場合、2年後に返却すれば8万円分の支払いが免除されるとします。しかし、返却せずに使い続ければ、その8万円も支払わなければなりません。つまり、「返却すること」を前提にしなければお得にはならないのです。
返却時の査定条件が厳しい
スマホの返却査定は想像以上にシビアです。ディスプレイの割れや液晶焼けはもちろん、背面の小さな擦り傷、端子部分の劣化なども減額の対象になります。これらは日常使用の範囲でも避けにくいものです。
「査定条件を満たさない場合、22,000円(不課税)の支払いが必要となります。」
(ソフトバンク公式サイトより引用)
つまり、「2年後に返せば0円」と言われても、現実には傷の有無や動作状態によって返却時の費用が変動するのです。筆者の知人は、iPhoneの角にわずかな欠けがあっただけで、査定不良とされ2万円近く請求されました。
精神的な負担も大きい
2年間の使用中、「傷をつけないように」「落とさないように」と気を使いながら使うことになります。ケースや保護フィルムを付けたとしても、使用感を完全に防ぐのは難しく、結果的に自由度が下がるのがこのプランの大きなデメリットです。
長期利用には不向き
3年以上同じスマホを使いたい方には、このプランはほぼ意味がありません。2年後に返却しなければ、残価分を支払う必要があり、結果的に定価購入より高くなるケースもあります。長期的に見ると、2年返却プランはコストパフォーマンスが悪くなることも多いのです。
スマホ2年返却デメリットの中でも最大の落とし穴「途中解約リスク」

このプランのもう一つの大きな問題が、「途中解約がほぼ不可能」である点です。契約期間中にキャリアを乗り換えたり、通信費を節約したいと思っても、返却プランがある限り身動きが取れません。
途中解約で残債一括請求
途中で契約を解約した場合、残りの端末代金をすべて一括で支払う必要があります。しかも、返却免除特典は適用されません。そのため、実質的に「2年間はキャリアに縛られる」構造になっています。
回線解約してもプログラム継続が条件
ドコモの「スマホおかえしプログラム」では、回線を解約しても返却すれば特典は使えると記載されていますが、裏を返せば「返却するまでプログラムを維持する必要がある」ということです。
「回線契約を解約しても、返却条件を満たすことで特典は利用可能です」
(NTTドコモ公式サイトより引用)
つまり、プログラムを途中でやめる選択肢は事実上存在しないのです。
返却期限を過ぎると違約金が発生
返却期限に遅れると、免除予定だった残価分の金額を「違約金」として請求されます。1日でも遅れるだけで8万円や10万円の負担になるケースもあり、スケジュール管理の重要性は非常に高いです。
筆者が感じた心理的な不自由さ
筆者はこの仕組みを調べながら、「これは所有しているようで、実は借りている状態」だと痛感しました。契約自由度が低く、途中解約もできず、破損リスクも背負う。利便性よりも制約の方が多い印象です。
スマホ2年返却プランの実際の利用者の声と体験談
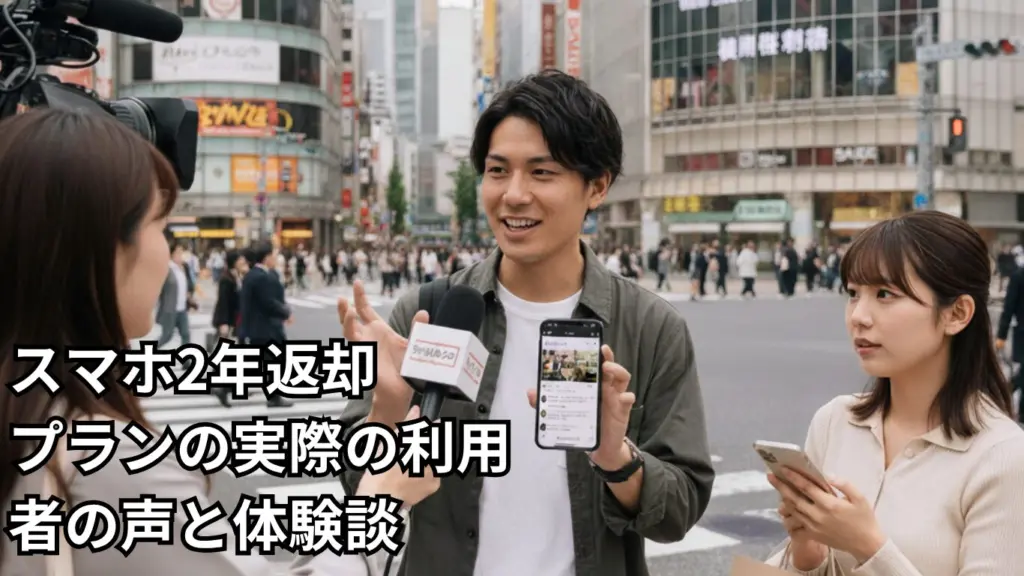
インターネット上では、2年返却プランを利用した人のさまざまな声が見られます。特に多いのは、「思ったより自由がなかった」「返却時の査定が厳しかった」という声です。
「返却査定で予想外の費用を取られた」
あるユーザーは、iPhoneを返却した際、わずかなフレームのへこみで2万2000円を請求されたと話しています。公式には「通常使用の範囲内」と書かれていても、実際の査定では想定外の減額があるようです。
また、格安SIMに乗り換えようとしたが「返却条件があるからまだ乗り換えられない」といったケースも多く見られます。結果として、通信費の節約チャンスを逃す人も少なくありません。
多くのユーザーが「買い切りの方が自由でストレスが少ない」と感じています。端末を自分のものとして所有する安心感は大きく、返却条件に縛られないメリットもあります。
スマホ2年返却デメリットを理解したうえでの賢い選び方

ここまでスマホ2年返却プランの注意点を見てきましたが、「結局、どう選べばいいの?」という疑問を持たれた方も多いでしょう。プランのデメリットを理解したうえで、あなたのライフスタイルに合った最適な選択をするための具体的な指針を紹介します。
自分が「長く所有したい派」か「常に最新を使いたい派」かを明確にする
スマホ2年返却プランは、端末を“所有”するのではなく“借りて利用する”プランです。そのため、「モノを大切に長く使いたい」タイプの人には向いていません。逆に、「常に最新機種を使いたい」「2年ごとに買い替えるのが前提」という人にとっては理想的な仕組みです。
筆者の知人は最新のiPhoneを毎年買い替えるタイプで、返却プランの利便性を高く評価していました。傷をほとんど付けずに使い、2年後にはほぼ新品同様で返却できたため、結果的に実質負担は少なかったそうです。このように、「自分の使い方スタイル」を明確にしてから契約を選ぶことが重要です。
返却条件と査定基準を必ず事前に確認する
返却条件はキャリアごとに異なります。たとえばソフトバンクの「新トクするサポート」では、破損・故障・液晶割れなどがある場合は免除が無効になり、22,000円を支払う必要があります。auの「スマホトクするプログラム」では、水没や改造も対象外です。
「査定条件を満たさない場合、免除の対象外となり、別途22,000円(税込)の支払いが必要です」
(ソフトバンク公式サイトより引用)
契約前に、どの状態までが「通常使用」とみなされるのかを確認し、必要に応じて店舗で実際の査定基準を聞くのが確実です。特に、日常の擦り傷やバッテリー劣化がどう扱われるかは要チェックポイントです。
返却前提なら、スマホ保険や補償オプションを活用する
もし返却プランを利用するなら、「スマホ保険」や「キャリアの端末補償サービス」に加入しておくと安心です。返却時に査定不良とされた場合でも、保険で修理または交換できる可能性があります。
ドコモの「ケータイ補償サービス」やauの「故障紛失サポート」などは、月額500〜900円程度で加入可能です。2年間で見れば1万円ほどの支出になりますが、査定不良で数万円請求されるリスクを考えると、保険としては安いものです。
返却プランの「免除金額」が本当にお得かをシミュレーションする
スマホの定価と、2年間で実際に支払う金額、返却時の免除額を具体的に比較してみましょう。例えば、15万円のiPhoneで「2年後に7万円免除」とされている場合でも、途中で傷がつけば免除が無効になるリスクがあります。中古市場での売却価格が8万円を超える可能性もあるため、一概に返却プランが得とは限りません。
筆者は実際に複数の機種で試算したところ、iPhoneシリーズでは中古市場の下取り価格が高いため、「自分で売却した方が得」になるケースが多いと感じました。Androidでも人気機種なら同様です。
返却期限を確実に守るための仕組みを作る
返却期限を過ぎると、免除予定だった金額が“違約金”として発生します。特に、郵送返却の場合は配送日数も考慮する必要があります。契約時に返却期限をスマホのカレンダーに登録し、1か月前に通知が来るよう設定しておくと安全です。
また、店舗返却よりも郵送返却の方が時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで行動することが大切です。
2年後に「返却しない場合」も想定しておく
返却しない=免除がなくなるという点は多くの人が見落とします。返却しない場合、残価分(例:7万円〜8万円)を支払う必要があり、総額では定価より高くなることもあります。途中で「このスマホを気に入ったから使い続けたい」と思っても、その時点で追加出費が避けられません。
筆者の友人はこの点を知らずに契約し、結果的に返却せず使い続けたことで、支払い総額が新品購入時より2万円以上高くなりました。このようなトラブルを避けるためにも、契約前に「返却しない場合の総額」を明確に計算しておくことが重要です。
買い切り+中古売却という「もう一つの賢い選択」
返却プランに不安を感じる場合は、「買い切りで購入し、2年後に自分で売却する」方法も検討しましょう。たとえば、iPhoneシリーズなら中古市場でのリセールバリューが非常に高く、2年後でも定価の50〜60%で売れるケースがあります。
実際に筆者は、iPhone 13 ProをApple Storeで買い切り購入し、2年後に中古買取サービスで売却したところ、7万5,000円で買い取られました。購入価格が14万円だったため、実質支払額は6万5,000円。これは返却プランよりもお得な結果でした。
公式キャンペーンや下取りプログラムも活用する
キャリアやメーカーが実施する下取りプログラムも見逃せません。Appleの「Apple Trade In」やドコモの「下取りプログラム」では、端末を返却することで次の購入にポイントを充てられます。返却プランより柔軟で、自由度の高い買い替え方法です。
「Apple Trade Inでは、お使いのiPhoneを下取りに出すと、新しい製品の購入価格が割引されます。」
(Apple公式サイトより引用)
将来的なキャリア変更の自由度も考慮する
返却プランに縛られていると、2年間は他社への乗り換えが難しくなります。特に通信費を節約したい人や、楽天モバイル・ahamo・povoなどへの移行を考えている人は注意が必要です。買い切りであれば、いつでも自由にキャリアを変えられます。
最終判断は「自由度」と「心理的ストレス」で考える
価格だけでなく、精神的な自由度も重要です。返却を気にしながら使うのがストレスに感じるなら、多少高くても買い切りを選んだ方が満足度が高くなります。スマホは毎日使うものだからこそ、「安心して使えるかどうか」が最も大切な判断基準になります。
筆者の結論:短期派なら返却プラン、長期派なら買い切り
筆者の結論としては、「2年周期で最新機種を使いたい人」には返却プランも有効です。しかし、「スマホを長く大切に使いたい人」や「自由にキャリアを選びたい人」には、買い切りがベスト。筆者自身は後者のタイプで、今後も買い切り+中古売却のスタイルを続けるつもりです。
どちらを選ぶにしても、重要なのは「返却条件・残価・自由度・ストレス」の4点を総合的に比較して、自分のライフスタイルに合った選択をすることです。
デメリットを理解した上で、どう選べばいいのかを考えましょう。
主要キャリア別 スマホ 2年返却 プログラムの利用時リスク詳細分析

ドコモ「いつでもカエドキプログラム」のリスクポイントと早期利用料
ドコモの「いつでもカエドキプログラム」は、24回目以降に端末を返却することで、あらかじめ設定された残価(24ヶ月目時点での端末の価値)の支払いが免除される仕組みです。
しかし、「いつでもカエドキプログラム+」の場合、22ヶ月目までに返却する「早期利用」を選択すると、早期利用料として12,100円の追加費用が発生します 。これは、早く新しい機種に買い替えたいというニーズに応えるためのサービスですが、その代償として明確なコストが設定されています。さらに、前述したように、早期返却時に故障が判明した場合、早期利用料に加えて故障時利用料(最大12,100円)が必要となるリスクも伴います 。
この構造は、単なる残債免除ではなく、利用期間に応じて費用が変動する複雑な金融オプション的要素を持っていることを示唆しており、ユーザーが「いつ買い替えるのが最もお得か」を正確に判断することを困難にしています。
au「かえトクプログラム」のリスクと仕組み
auの「かえトクプログラム」(及びそれに類する現行プログラム)も、48回払いのうち、所定の期間(例えば24ヶ月目まで)に端末を返却し、新しい機種に機種変更することで、残りの残債支払いが免除されるシステムを基本としています。
auのプログラムも、その他のキャリアと同様に、端末の破損や機能不全による査定落ちリスクが最大の懸念事項です。査定基準の厳格さが、ユーザーに残価免除のメリットを得られないという金銭的なリスクを転嫁している点は、十分に留意しなければなりません。
ソフトバンク「新トクするサポート」の特典A/特典Bの複雑性と利用期限
ソフトバンクの「新トクするサポート」は、48回払いで購入し、特定の期間に返却することで残債が免除される仕組みですが、特典Aと特典Bという二段階の複雑な利用期間設定がされています 。
特典Aは、購入から13ヶ月目から24ヶ月目までに機種の回収・査定完了が求められ、特典Bは25ヶ月目以降の利用申し込みが条件となります 。この利用期間の厳密な設定が、ユーザーにとって大きなリスクとなります。特に特典Aのように期間が限定されている場合、ユーザーが手続きの期限を見落としたり、手続きに手間取ったりすることで、特典利用の機会を完全に失い、結果として残債全額を負担しなければならない事態に陥る危険性があります。
この複雑な条件分岐は、消費者が契約の本質を正確に理解するのを阻害し、「計算外の出費」が発生する可能性を高める要因として機能しています。
スマホ2年返却デメリットを理解した上で賢く利用するためのまとめ
- 返却プランは実質レンタル契約であり、所有権は利用者にない
- 査定基準が厳しく、傷や汚れで2万円以上の負担が発生することも
- 途中解約不可で、キャリアを2年間縛られる
- 返却しない場合は全額支払いで実質的に割高
- 返却期限を過ぎると違約金が発生するため注意が必要
残価設定型購入プログラムは、最新のスマートフォンを低コストで使い続けたい消費者にとって魅力的な選択肢であることは間違いありません。しかし、その「最大半額」というメリットの裏側には、査定落ちリスク、キャリアへの依存、そして経済的機会損失といった多くの デメリット が潜んでいます。
これらのプログラムは、「割引」というよりも「2年間のリース契約」の側面が強いと認識することが、賢く利用するための第一歩です。端末は自分の資産ではなく、キャリアに返却する義務がある借り物である、という意識を持つべきです。
高額な追加料金(22,000円や12,100円など)の発生という大きなリスクを避けるためには、キャリアが提供する補償サービス(smartあんしん補償など)への加入を実質的に必須コストとして予算に組み込む必要があります 。補償サービス料を加味した上で、2年間の総支払額を再計算し、本当に経済的なメリットがあるのかを冷静に判断することが求められます。
また、長期的な視点での経済性の評価も重要です。2年ごとの買い替えサイクルは、最新機種を使える満足感をもたらしますが、端末を長期利用(4〜5年)した場合の生涯コストと比較し、自身の利用頻度や経済状況に照らして真に最適な選択かを検討することが不可欠です。
契約を結ぶ前には、以下のチェックリストを用いて、潜在的なリスクを徹底的に確認することをお勧めいたします。
- 査定基準の厳格性の確認: 査定基準(特に破損や欠陥の定義)を契約書または提供条件書で読み込み、許容範囲がどれほど狭いかを把握したか。
- 実質的な月額負担額の計算: 端末の分割料金に加え、補償サービス加入後の月額費用、および早期返却を検討する場合の早期利用料を含めた総負担額を計算したか。
- 端末管理の自信: 2年間、端末を常に新品同様に保ち、査定落ちを完全に避ける自信があるか。
- 所有権のオプション評価: 2年後に返却せず、残債を支払いきって端末を完全に所有する選択肢を選んだ場合の総支払額と、その場合の経済的価値を把握しているか。
残価設定プログラムは、その複雑性ゆえに、情報を十分に持たない消費者にとって予期せぬ落とし穴となり得ます。透明性の低い契約に対しては常に慎重な姿勢を保ち、自身のリスク許容度と照らし合わせて判断することが、現代のスマートフォン購入において最も重要であると言えます。
「最新スマホを安く使いたい」というニーズに応えるプランではありますが、条件や制約が多いため、内容を理解せずに契約すると後悔する可能性があります。長く使いたい人には買い切り型の購入がおすすめです。